「これじゃLinux一択だろ」
「ユーザーが望んでない機能を勝手に押し込むな」
Windows 11にCopilotや新しいAI機能が次々と組み込まれるなか、海外のユーザーや開発者から、かなりストレートな怒りの声が上がっています。
その一方で、Microsoft AIのムスタファ・スレイマンCEOは「AIの能力に感動していない人がいるのは本当に信じられない」と発言し、油に火を注いだ形になりました。
いま米国では、「AIはすごい」派と「AIを押し付けるな」派の温度差 が、WindowsというOSを舞台にむき出しになっています。
本記事では、海外メディア、専門家、投資家のコメントを追いながら、このAI論争の本質と、私たちがどう付き合うべきかを整理していきます。
目次
何が起きたのか──「AIに感動しないのはマインドブローイング」発言
発端のひとつは、テックメディア Windows Central が報じたムスタファ・スレイマン氏のコメントです。彼はX(旧Twitter)上で、Copilotや画像・動画生成を含む現在のAI技術に対して「AIを“しょぼい”“期待外れ”と呼ぶシニシズムが多い」「これだけ賢いAIと流暢に会話できるようになったのに、感銘を受けない人がいるのは mindblowing(衝撃的)だ」と述べました。Windows Central+1
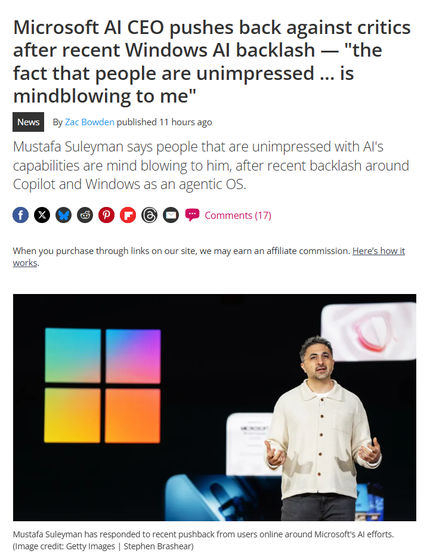
この投稿は、直前にあった別件の炎上とも重なります。Windows部門トップのPavan Davuluri氏が「WindowsはAgentic OS(AIエージェントが自律的に動くOS)へ進化していく」とXに投稿したところ、ユーザーから
「まずバグを直せ」「AIを押し付けるな」
という批判が殺到し、返信機能をオフに追い込まれたのです。Windows Central+1
そこに「AIすごいでしょ? これで感動しないのは理解できない」というトーンの発言が重なったため、ユーザーのフラストレーションを理解していないトップという受け取られ方をしてしまいました。
お騒がせCEO
過去には、こんな発言も お騒がせCEOと言われている。
MicrosoftのAI開発部門であるMicrosoft AIのムスタファ・スレイマンCEOが、オープンウェブ上にコンテンツを公開した瞬間、誰でも自由にコピーして使用できる「フリーウェア」になるという考えを自身が持っていることを打ち明けました。テクノロジーメディアのThe Vergeは、「誤った考えを持っている」と批判しています。
Microsoft’s AI boss thinks it’s perfectly OK to steal content if it’s on the open web - The Verge
https://www.theverge.com/2024/6/28/24188391/microsoft-ai-suleyman-social-contract-freewareWindowsのAI製品への批判を受けMicrosoftのAI責任者が冷笑系にウンザリ、「超賢いAIに感心しないなんて信じられない」と語る - GIGAZINE
https://gigazine.net/news/20251120-microsoft-ai-ceo-against-windows-backlash/
ユーザー・開発者が怒っているポイントはどこか
スレイマン氏のコメントをめぐる反応は、ただの「AI嫌い」ではなく、ここ数年で積み上がった不信感の爆発にも見えます。代表的な論点を整理すると、こんな構図が浮かび上がってきます。
「まずは普通に動け」という基本要求
The Verge は、Windows 40周年の特集の中で、「Microsoftは“Your canvas for AI(AIのキャンバスとしてのWindows)”というスローガンを掲げる一方で、ユーザーは基本的な安定性やUIの混乱、広告的要素の増加に不満を抱いている」と指摘しています。The Verge+1
RS Web Solutions も、Windows 11のアップデートで回復環境(WinRE)が壊れた件などに触れ、「Microsoftはユーザーのニーズより、自分たちが理想とするOS像を優先しているように見える」とコメント。ユーザーの中には「2015年頃のソフト+今のセキュリティだけでいい」「余計なAI機能はいらない」という声すらあると伝えています。RS Web Solutions
Recallと「スパイウェア扱い」の記憶
AIへの不信感を決定的にしたのが、Windows 11用の機能「Recall」です。これはPC画面を数秒おきに自動でスクリーンショットし、それを検索できるようにする仕組みですが、発表直後からセキュリティ研究者やプライバシー団体から 「ほぼスパイウェア」 と批判されました。Digital Rights Asia+1
Windows Central も、Recall騒動を「ユーザーの信頼を完全に失わせたPRの大失敗」と評し、「多くの人が“これを機にLinuxかMacに乗り換える”と言い出した」と報じています。Windows Central
その後MicrosoftはRecallを「既定でオフ」「Opt-in(ユーザーが自分でオンにする方式)」に変更しましたが、一度ついた**「Windows=何でも勝手に記録するOS」というレッテル**は簡単には剥がれません。The Verge+1
「AIがOSに深く埋め込まれすぎている」という恐怖
オーストラリアの掲示板 Whirlpool では、「Windows 11 25H2ではCopilotがOSに深く埋め込まれていて、完全に無効化することがほぼ不可能だ」「事実上のスパイウェアだ」といった極端な言い方も散見されます。Whirlpool.net.au
Hacker News でも、「今がLinuxへ移行するベストタイミングだ」「Windowsを入れるのは、PCを企業に乗っ取らせるようなものだ」という辛辣なコメントが人気上位に来ており、「Windows = SkyNet OS」というジョークが真顔で語られる空気すらあります。Hacker News+1
開発者コミュニティからは、「開発者が求めているのは、予測不能なAIエージェントではなく、安定したツールチェーンとOSのコントロールだ。そういう意味で、ビルダーはMacかLinuxを選ぶ」という声も目立ちます。こうした文脈を踏まえると、ユーザーが投げている「これじゃLinux一択」というフレーズは、単なる冗談ではなく信頼の残高が尽きかけているサインとも言えます。
それでもMicrosoftとスレイマンCEOがAIを推す理由
一方で、Microsoft側の論理もまったく理解不能というわけではありません。
スレイマン氏は「自分はNokiaの“Snake(昔の携帯ゲーム)”を遊んでいた世代だ。そこからAIと自然に会話できて、あらゆる画像・動画を生成できるところまで来たのに、これを“しょぼい”と言われるのは信じられない」と語っています。Windows Central+1
Jeez there so many cynics! It cracks me up when I hear people call AI underwhelming. I grew up playing Snake on a Nokia phone! The fact that people are unimpressed that we can have a fluent conversation with a super smart AI that can generate any image/video is mindblowing to me.
— Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) November 19, 2025
また、Microsoft内部の開発者や社員からは、「社内でCopilotを使うと、コードレビューや仕様書作成が本当に速くなる」「OfficeのCopilotも法人向けにはかなり実用レベルだ」といったポジティブな証言も出ています。Reddit+1
さらに、同社が共有したゲーマー向け調査では「79%がAIによるゲームプレイ支援に前向き」という結果もあり、一部のセグメントではAIへの受容度は高いことも事実です。inkl
つまりMicrosoftから見ると、
-
すでに法人市場ではCopilotが成果を上げている
-
一般ユーザーも、きちんと使ってくれれば便利さを理解してもらえるはず
-
Windowsを「AIエージェントが動くOS」に変えるのは戦略的に必須
というストーリーがあり、だからこそ「なのに、なんでここまで冷ややかなの?」というスレイマン氏の率直な驚きが出てくるわけです。
テックメディア・専門家・投資家はどう見ているか
「ビジョンは分かる、でもタイミングと信頼が最悪」
The Verge や ITPro などのテックメディアは、「WindowsをAgentic OSにする構想自体は、技術的には理解できる」としつつ、**「現状のCopilotの出来と、ユーザー側の警戒心を考えると、突っ走るにはタイミングが悪すぎる」**と指摘しています。実際、The Verge は検証記事の中で「広告で示されるような“シームレスに何でもやってくれるCopilot”には程遠い」と辛辣な評価を下しています。Windows Central+1
ITPro も「MicrosoftはWindowsをAgentic OSにすることに固執しているが、ユーザーから見れば“AIスロップ(AIまみれのジャンク)”にしか見えないリスクがある」と警鐘を鳴らしています。IT Pro+1
投資家視点:成長エンジンだが、ブランド毀損リスクも
投資家やアナリスト視点では、AIはもちろんMicrosoftの成長ストーリーの中核です。クラウド(Azure)、Office、GitHub Copilotなど、すでに売上に直結している領域も多く、「AIをやめる」という選択肢はほぼありません。
ただし、Recall騒動や今回のような炎上を経て、「Windowsブランドの信頼毀損が長期的なリスクになりつつある」という見方も出てきました。Windows Central も、「AIへの異常な執着が、既存ユーザーをMacやLinuxへ押しやる“逆効果”になっている」と指摘しています。Windows Central+1
短期的にはAI投資は市場から評価されても、「Windowsという土台を壊すほどの嫌われ方」をし始めているなら、それは中長期のリスクと見なされる――そう考える投資家も増えているのが現状です。
日本のユーザーはどう向き合うべきか
日本からこのAI論争を眺めると、「結局、自分のPCはどうなるの?」というのが一番気になるところだと思います。
今のところ、
-
Agentic OS 的な機能は デフォルトでオフ にする方針が明言されている
-
Recall も炎上を受けて「完全Opt-in+追加のプライバシー保護」が加えられている
という意味では、いきなり「勝手に全部オン」にされるリスクはやや減っています。The Verge+1
とはいえ、
-
Windows Updateのたびに、知らないAI機能が増える
-
その説明やオフの仕方が分かりづらい
-
そもそも基本的な安定性やUI改善が後回しにされている
と感じるユーザーが増えれば、海外と同様に「もうMacかLinuxでいいや」という流れが日本でも強まる可能性は十分にあります。
個人的には、
-
メイン環境では新しいAI機能は基本オフ
-
興味があればサブ環境や仮想マシンで「どこまで何をしているか」を確認する
-
自分のワークフローに本当に効くAIだけを選んで使う
という、ちょっと「距離をとった付き合い方」が現実的な落としどころかなと思います。
まとめ──“AIすごい”と“普通に動いてほしい”のすれ違い
今回のスレイマンCEOの発言は、「AIはすごいからもっと感動してくれ」という開発側の興奮と、
「いや、その前にOSを普通に使わせてくれ」というユーザー側の疲れ
が、真っ向からぶつかってしまった象徴的な出来事でした。
AIの進化自体は素晴らしいし、仕事や創作の現場で役立つ場面も確実に増えています。ただ、OSという「生活インフラ」においては、“すごい未来”よりも“壊れない現在”が優先されるのもまた事実です。
WindowsとAIをめぐる論争は、これからもしばらく続くでしょう。大事なのは、AIを盲目的に拒否することでも、全面的に受け入れることでもなく、
「どこまでを許容して、どこからはNOと言うのか」を自分の基準で決めること。
その意味で、今回の騒動は、私たち一人ひとりに「自分のPCとAIの距離感」を問い直す良いきっかけなのかもしれません。
ひとりごと
OSの進化の到達点がエージェントというのはわかります。
スタートレックのようなSFドラマでは、すべての機能がAIを通じて行われていて、人は、判断を下すという行為が中心となります。
と言っても アンドロイドのデータ少尉は、絵を描き、音楽を自ら演奏し、演劇で役者になるという行為を行っている。
データ少尉が、人に近づきたいという願望(のようなもの)でプログラムされているとして、人が持つ可能性をAIが潰してはいけない。
ということを暗示しているのではないだろうか?
OSの話にもどすと AIを使うことはごく自然になってきたと言え まだまだ 不便なことが多いのも事実
確かにプログラミング、議事録、ドキュメント作成など便利と言えば便利ですが、中途半端に介入されるのも「邪魔者扱い」されることもある。
CEOが「AIに感動しない人がいるのは信じられない」なんて言うこと自体「うかつな行為」だったと思いますが、騒動の背景には、米国でAIの普及で大規模なリストラがはじまりつつあることも背景にありそうです。
AIに対する不安と現実的な雇用問題 日本でもそろそろ問題になりそうです。

